プロが実践するリバランス術
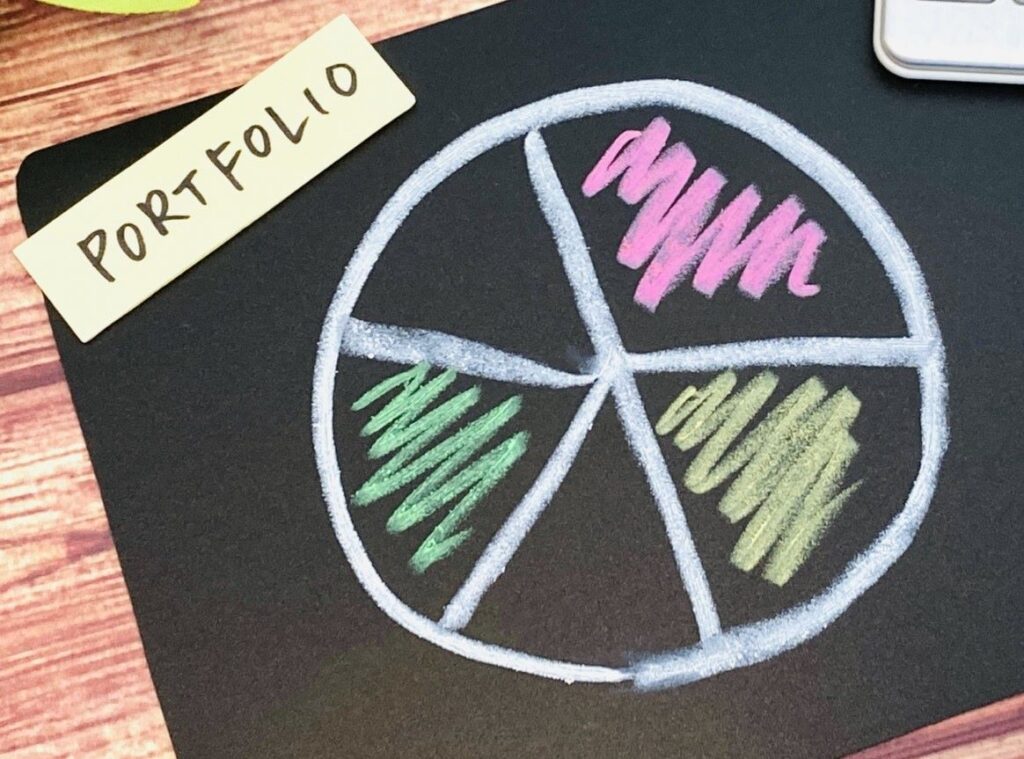
株式市場が急落すると、多くの投資家は「どこまで下がるのか…」と不安に包まれます。しかし、プロの投資家はそんな時こそ冷静にポートフォリオ(資産配分)を見直しています。
なぜなら、急落によって資産全体のバランスが大きく崩れてしまうからです。
今回はその“資産の偏り”が生むリスクと、プロが行っているリバランス(再調整)の考え方を、具体例とともにわかりやすくご紹介します!
急落時に起こる「偏り」とは?

急落時には以下のようなことが起こります。
- 株式が大きく下がる → 他の資産と比べたときの“割合(比率)”が変わる
- 特定セクター(ハイテクなど)だけ保有 → 偏りが加速
例:ハイテク株中心に投資していた場合、その分下落幅が大きくダメージも集中
結果、リスクの高い状態になってしまうのです。
プロ投資家は「リバランス」で対応!

リバランスとは、崩れたポートフォリオ(資産配分)を、自分のリスク許容度に合わせて元に戻す作業のことです。
具体的なリバランスの方法
① 債券(さいけん)や現金の比率を再確認
例えば、あなたの資産配分が当初
「株式40%・債券30%・現金30%」だったとします。しかし株価が急落した際、「今がチャンスだ」と思って現金の一部で株を買い増したとしましょう。
すると、株の比率が相対的に高くなり、
「株式50%・債券30%・現金20%」というような感じにバランスが崩れてしまう可能性もあります。
このまま放置しておくと、株式という値動きの大きい資産に偏ってしまい、リスクが高まります。こうしたときに必要なのが「リバランス(資産配分の調整)」です。
簡単にいうと、「元のバランスに戻すように売買すること」。
この場合、株を一部売って、現金に回すことで、リスクを抑えた構成に戻します。
こうすることで、リスクをコントロールしつつ安定的に資産運用ができるというメリットがあります。
債券(さいけん)とは?

債券とは「お金を預けて、あとで利子と一緒に返してもらう」投資のことです。
例えば、
国や会社が「お金を借りたい」と思ったときに出すのが債券なのですが、もしあなたがその債券を買った場合、「その国や会社にお金を貸してあげる」という立場になります。
すると、決まった期間ごとに利息(クーポン)を受け取りながら、最後には預けたお金(元本)も戻ってくるというしくみになっています。
債券の具体的なイメージ
- 満期5年、利率2%の債券を100万円分買ったとします。
- 毎年2万円の利息を5年間もらい、
- 5年後に100万円が返ってくる。
→ こういった安定収入を狙えるのが債券です。
債券にはどんな種類があるの?
① 国債(こくさい)
国が発行する債券です。もっとも安全性が高いとされます。
- 例:日本国債、米国債、ドイツ国債など
- 特徴:利回りは低めだけどリスクも低い
② 地方債(ちほうさい)
都道府県や市区町村が発行する債券。
- 例:東京都債、大阪市債など
- 公共事業の資金に使われる
③ 社債(しゃさい)
企業が発行する債券です。
- 例:トヨタの社債、ソフトバンクの社債など
- 企業の信用力によって利回りやリスクが変わる
④ 外貨建て債券
外国の通貨で発行される債券。
- 例:米ドル建てのブラジル国債、豪ドル建ての社債など
- 為替の影響を受けるが、金利は高めの傾向あり
⑤ 新興国債券
経済発展中の国(インド、インドネシア、トルコなど)が発行する債券。
- リターンが大きい反面、政治・経済の不安定さからリスクも高め
② 防御的セクターにシフト
急落時でもダメージが比較的少ないディフェンシブ銘柄に目を向けます。
| 防御的セクター | 具体例 |
|---|---|
| 生活必需品 | 食品メーカー、日用品大手など |
| 医薬品 | 製薬会社、ドラッグストア関連など |
これらは「景気に関係なく必要とされる」ため、下落局面で比較的安定しています。
③ できるならば、「通貨」や「地域の分散」も検討する
日本株(米国株でも)に偏りすぎていると、特定の国のリスクをまともに受けてしまいます。
例:
たとえば、資産の大半を日本株に集中させていたとします。
ところが…
- 日銀の金融政策の変化
- 消費税増税や政局の不透明感
- 高齢化による国内市場の成長鈍化
など、日本特有のリスクが浮上すると、資産全体が大きく影響を受けてしまう可能性があります。
そこで「分散投資」
こうした偏りを避けるために、一部の資産を以下のように分散するのが効果的です。
- 米国株や欧州株 ⇒(グローバルな経済成長に乗る)
- 新興国株 ⇒(成長率の高い地域に分散)
- 外貨建て債券 ⇒(為替リスクを逆に活用)
- 金やREIT(不動産投資信託)⇒(株と値動きが異なる資産)
こうすることで、日本の経済が不安定になったとしても、他の地域や資産がカバーしてくれる可能性が高まり、リスク分散になります。
投資先を分けておくことで影響を受けにくくなり、資産をより安定的に守り育てることができます。
代表的な「通貨」と特徴

なぜ通貨の分散が大事なの…?
- 日本の金利や経済状況が悪化して円安が進んだ場合でも、外貨建て資産は価値が上がる可能性がある。
- 世界情勢に応じて、異なる通貨が異なる動きをするため、資産全体の値動きを安定させやすくなる。
| 通貨 | 特徴 |
|---|---|
| 🇺🇸米ドル(USD) | 世界の基軸通貨。安定性が高く、情報も豊富。金利が高めの傾向もあり、利息狙いにも◎ |
| 🇪🇺ユーロ(EUR) | 欧州の共通通貨。取引量も多く、分散先としてよく使われる |
| 🇦🇺豪ドル(AUD) | 資源国通貨で、金利が比較的高い。景気敏感通貨でもある |
| 🇨🇭スイスフラン(CHF) | 安定性が高く、リスク回避時に買われやすい「安全資産」 |
| 🇧🇷ブラジルレアル(BRL)など新興国通貨 | 高金利だが、値動きが大きくリスクも高い。少額での分散が基本 |
⚠️【外貨建て資産の注意点】
- 為替リスクがある
→ 円高になると、外貨建ての資産価値は目減りする場合がある - 手数料がかかる
→ 外貨への両替や外貨建て商品の購入時に、スプレッド(売買差)などのコストが発生する - 情報収集が大切
→ 為替や海外の金利・経済動向など、日本と違う視点でのチェックが必要になる
外貨建て資産は、うまく使えば「通貨の分散」や「高金利の活用」ができますが、為替の動きによって損益が大きく変わるので、バランスと理解が大切です。
まとめ:相場が荒れた時こそ、資産配分を整えよう
相場の急変時、「どこが底か?」を探す前にやるべきことがあります。
それは、自分のポートフォリオがどうなっているかを客観的に見ること。
- 株だけが極端に増えていないか?
- セクターが偏っていないか?
- 債券や現金が少なすぎないか?
上記のようなことを確認することによって…- リスクの過剰集中を防げる
- 感情的な売買を減らし、ルールベースで判断できる
- “安く買って高く売る”のサイクルを自然に実現しやすい
こうした視点を持てるかどうかが、長期で資産を守り育てる投資家の分かれ道になります。






















