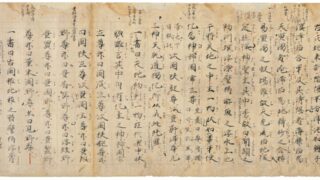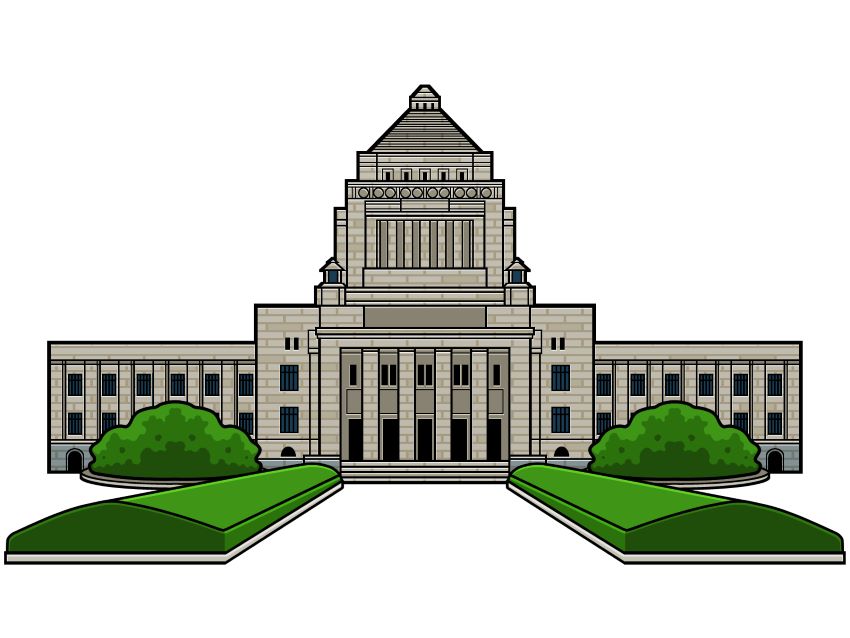政治・法律の一般常識クイズ
Q1. 日本の現憲法は何年に施行されたか?
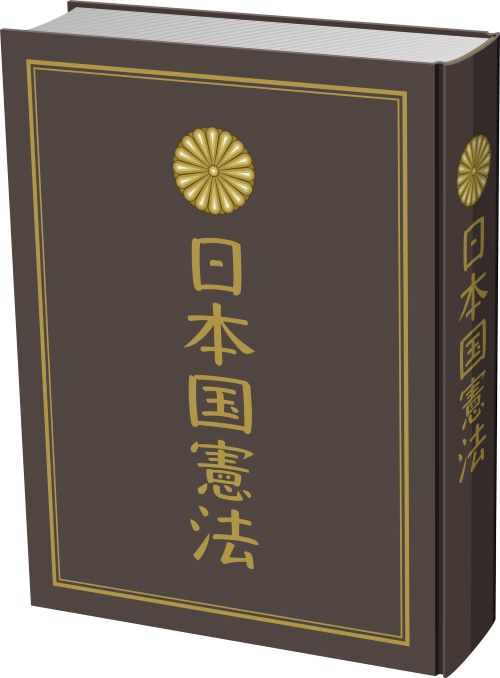
A. 1947年
解説:
日本国憲法は、1947年5月3日に施行されました。この日は「憲法記念日」としても知られています。
なぜ、日本国憲法は1947年5月3日に施行した?
日本国憲法は、第二次世界大戦後の日本の戦後復興と民主化を進めるため、アメリカ占領下で制定されました。
1947年5月3日に施行されたのは、戦前の軍国主義体制を一新し、平和主義・民主主義を基盤にした新しい国家を作るためです。
この憲法により、天皇制は象徴的なものとなり、国民の基本的人権が保障されました。
Q2. 日本の内閣制度は、何年に創設されたか?

〔初代内閣総理大臣 伊藤博文〕
A. 1885年
解説:
内閣制度は、明治時代の1885年に創設されました。内閣制度の創設により、内閣は日本の最高行政機関となりました。
なぜ、内閣制度ができた?
1885年、明治政府は太政官制(古代から続く政治制度)を廃止し、新たに内閣制度を創設しました。
これは、日本を近代国家へと発展させるために、政治の仕組みを西洋型に改革する必要があったためです。
従来の太政官制では、権限や役割分担があいまいで、急速な近代化には対応できませんでした。
そこで、初代内閣総理大臣に伊藤博文を任命し、各大臣がそれぞれの行政分野を担当する明確な組織に改め、効率的で責任のある政治運営を目指しました。
Q3. 日本の議会の名称は?
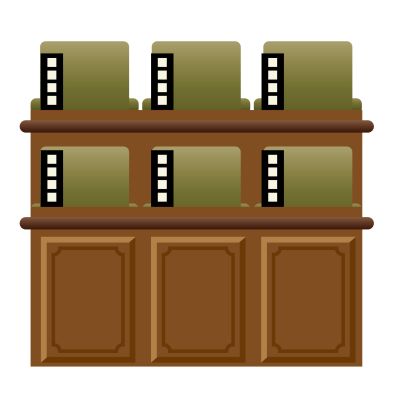
A. 国会
解説:
日本の議会は「国会」と呼ばれ、衆議院と参議院の2院制で構成されています。
Q4. 日本の衆議院議員の任期は何年か?

A. 4年
解説:
衆議院議員の任期は4年ですが、解散によって途中で任期が終了することもあります。
Q5. 日本の参議院議員の任期は何年か?

A. 6年
解説:
参議院議員の任期は6年であり、3年ごとに半数が改選されます。
Q6. 日本の憲法第9条で禁止されているのは?
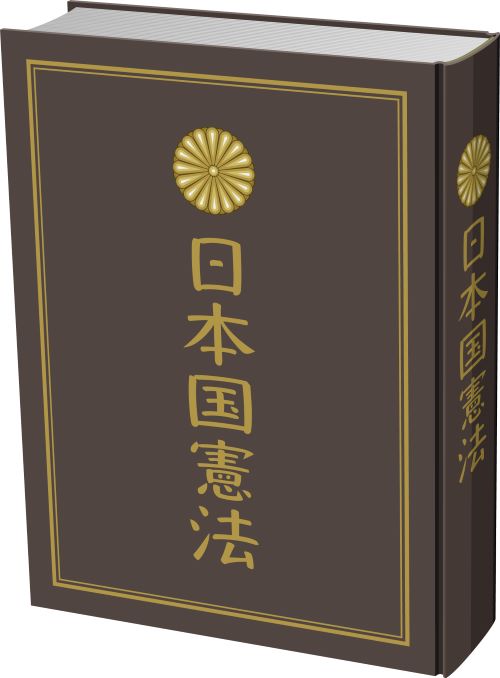
A. 戦争の放棄、戦力の不保持
解説:
日本国憲法第9条は、戦争を放棄し、戦力を保持しないことを規定しています。この条文は日本の平和主義の象徴とされています。
Q7. 日本の裁判所の中で最高裁判所はどのような位置づけですか?

A. 最上級(最高位)の裁判所
解説:
日本の最高裁判所は、国内で最上級の裁判所であり、憲法や法律の解釈について最終的な判断を下す権限を持っています。
Q8. 日本における「議院内閣制」とは何か?
A. 内閣が国会の信任を受けて行政を行う制度
解説:
議院内閣制は、内閣が国会(衆議院・参議院)の信任(しんにん)〔信頼して任せること〕を受けて行政を行う制度です。日本もこの制度を採用しています。
Q9. 日本の衆議院と参議院の違いは何か?

A. 任期、改選時期、議員数
解説:
衆議院と参議院は、いずれも国会を構成する二つの議院ですが、その性格や役割にはいくつかの違いがあります。
主な違いとして、まず任期が挙げられます。衆議院の任期は4年ですが、解散があるため、実際には任期途中で選挙になることがよくあります。一方、参議院の任期は6年で、解散はなく、3年ごとに半数が改選される仕組みです。
また、議員数も異なります。2025年現在、衆議院は465人、参議院は248人です。
選挙制度も異なり、衆議院は比例代表〔政党の得票数(政党への投票数)に比例して、議席が配分される制度〕と小選挙区〔1つの選挙区から1人だけ当選する制度〕の並立制、参議院は比例代表と都道府県ごとの選挙区を組み合わせています。
さらに、衆議院は予算案の先議権や、参議院よりも強い権限(法律案の再可決など)を持つことから、「優越(ゆうえつ)」される場面もあります。
Q10. 日本の「天皇」はどのような役割を持っているか?

A. 日本国の象徴であり、国家の統一を象徴する存在
解説:
日本の天皇は「象徴天皇制」に基づき、政治的権限を持たず、国家の象徴としての役割を果たしています。