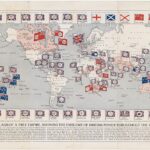盆踊りの起源

夏になると各地で開催される盆踊り。提灯の灯り、太鼓の音、浴衣姿の人々——。
どこか懐かしく、心温まる日本の風景ですが、この風習はいったいどこから生まれたのでしょうか。
ここでは、盆踊りの起源から、地域ごとの特徴、そして現代まで続く理由までをわかりやすく解説します!
そもそも「盆踊り」とは?

盆踊りは、日本のお盆の時期〔8月中旬が一般的〕に行われる踊りの行事です。
お盆は、先祖の霊を迎え、供養する期間。この期間に踊る理由は、もともと仏教行事の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来します。
「盂蘭盆会」は、古代インドの供養儀式「ウランバナ(Ullambana)」が中国を経て日本に伝わり、やがて日本で踊りと結びついて発展しました。
盆踊りの起源は「念仏踊り」

盆踊りのルーツは、平安時代末期から鎌倉時代にかけて広まった「念仏踊り」とされています。
これは、念仏を唱えながら踊ることで極楽往生〔死後に極楽浄土へ生まれ変わること〕を願う宗教的な踊りでした。
やがて、この踊りが地域ごとの民謡や風習と結びつき、先祖を供養しつつ、村人同士が集う娯楽としての要素も加わっていきました。
そして、室町時代には現在の盆踊りの形に近いスタイルが生まれています。
七夕は7月7日と8月7日どっち…?
なぜ、お盆に踊る?

お盆は「あの世」と「この世」が近づく時期とされます。
先祖の霊が里帰りするこの期間に、踊りや音楽で迎え入れ、感謝を伝え、再び送り出す——それが盆踊りの意味です。
太鼓や笛の音は、霊を呼び寄せると同時に、村全体の心を一つにまとめる役割も果たしていました。
お彼岸の意味とお墓参りに行く理由
地域ごとに違う踊りと音楽
盆踊りは日本全国で行われますが、踊り方や曲調は地域ごとに大きく異なります。
西馬音内(にしもない)盆踊り(秋田県)
黒頭巾や編み笠を被った幻想的な姿。

郡上(ぐじょう)おどり(岐阜県)
夜通し踊る「徹夜おどり」で有名。

阿波(あわ)おどり(徳島県)
勇壮で陽気なリズムと掛け声が魅力。

こうした違いは、各地域の歴史や気候、信仰と密接に関係しています。
まとめ:盆踊りは過去と未来をつなぐ踊り

盆踊りには長い歴史があり、その形や意味は地域によって少しずつ異なります。
ある地域では農作物の豊作を祈る行事として、また別の地域では亡くなった人の魂を見送る「送り盆」として行われてきました。
時代が進むにつれて宗教的な色合いは薄れ、今では夏の夜を彩る娯楽や地域の交流の場として親しまれています。
それでも、太鼓の音や踊りの輪の中には、先人たちが大切にしてきた「感謝」と「絆」の思いが、今も変わらず息づいているのです。